歯に良い栄養って?日本人はカルシウム不足!牛乳やオーツミルクで賢く補給

皆さん、こんにちは。
上尾市の麻生デンタルクリニックです。
皆さんは、毎日の食事で「カルシウム」を十分に摂取できていますか?
じつは歯にとって「カルシウム」は切っても切れない存在で、歯の健康を保つためにとても重要な栄養素なのです。
ですが日本人の「カルシウム」摂取量は、厚生労働省が発表する推奨量に明らかに届いていないのが現状です。
そこで今回は、不足しがちなカルシウムを効率よく、そして手軽に補給する方法をご紹介していきたいと思います。
麻生 明伸 院長

医院名:麻生デンタルクリニック
所在地: 〒362-0001 埼玉県上尾市大字上824-3
監修者:麻生 明伸 院長
Contents
歯に良い栄養って?
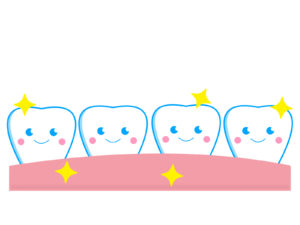
「カルシウム」は歯に良い栄養素の代表として挙げられることが多いですが、じつは歯に良い栄養素は「カルシウム」以外にも存在します。ここでは歯に良いとされる食材についてや、それらの栄養素が豊富に含まれる食材について紹介していきます。
カルシウム

「カルシウム」は、食後にむし歯菌の「酸」によって溶け出してしまった歯の成分の修復(再石灰化)をサポートをする栄養素です。
「カルシウム」が不足すると、この再石灰化のバランスが崩れてむし歯になるリスクが上がってしまうため、カルシウム不足にならないように気を付ける必要があります。
「カルシウム」は、小魚(煮干し30g)に約660mg、牛乳コップ1杯なら約220mg、チーズ(6切れ入りのプロセスチーズ)1切れは約150mg、小松菜1房(ゆで)なら約225mg含まれています。
タンパク質

「タンパク質」は歯の土台を作り、カルシウムの吸収を良くする作用があります。
また筋肉や肌、髪など身体のもとを作るために必要な成分でもあるので、しっかり栄養素を摂取しておきましょう。
「タンパク質」は、するめ100gのパックに約21g、牛リブロース(焼き)200gで約40g、ゆで卵2個約12g含まれています。
ビタミンA

「ビタミンA」は、歯の表面にある「エナメル質」を強化するために大切な栄養素です。
また歯への作用以外にも、皮膚の粘膜や目を健康に保ち、抵抗力も高めてくれる役割もあります。
「ビタミンA」は、1食の適量レバーペースト10g約0.13mg、かぼちゃ1/4切れ約0.8679mg含まれています。
ビタミンC

「ビタミンC」は、歯のエナメル質の下にある組織「象牙質」を作り、強くするために大切な栄養素です。
またコラーゲンを作るために必要な栄養素でもあり、さらに免疫力を強化してくれる役割もあります。
「ビタミンC」は、ブロッコリー(電子レンジ調理)1個まるごと約280mg、キュウイ(黄肉種)1個約140mg、なつみかん1個約32mg含まれています。
ビタミンD

「ビタミンD」は、カルシウム吸収率を上げる作用があります。
さらに骨の成長を促進したり、カルシウムの血中濃度を調節したりする役割もあります。
「ビタミンD」は、干し椎茸2個に約1㎍、しらす干し10gに約6.1㎍含まれています。
栄養バランスの良い食事が基本!

丈夫な歯を作るためには、「カルシウム」や「リン」などのミネラルはもちろん、その他にも良質の「たんぱく質」や「ビタミン」などを、バランス良く食事に取り入れることがとても大切です。
またお肉や小魚、食物繊維たっぷりの野菜など、噛み応えのある食材も取り入れることで、噛む回数が増え、顎の発育も促します。
さらに、噛む回数が増えれば唾液分泌も促進するため、唾液の「抗菌作用」が働いて、免疫機能を高めて感染予防にもつながります。
日本人のカルシウム不足は慢性的!
栄養バランスの良い食事が基本であるにも関わらず、日本人は慢性的なカルシウム不足だといわれています。
というのも、毎年行われる「国民健康・栄養調査(※令和2・3年はコロナウイルスの影響で中止)」では、日本人のカルシウム摂取量が、推奨量を常に下回っています。
さらにカルシウム推奨量のみならず、「推定平均必要量(50%の人が必要量として満たすもの)」さえも下回る年代もあります。
どれくらいカルシウム不足?
では実際に、日本人はどのぐらいカルシウムが不足しているのでしょうか?
以下は、2020年度に行われた厚生労働省による「1日のカルシウムの食事摂取基準(推奨量)」を表にまとめたものです。
年齢 / 男性 / 女性
8~9歳 / 650mg / 750mg
10~11歳 / 700mg / 750mg
12~14歳 / 1,000mg / 800mg
15~17歳 / 800mg / 650mg
18~29歳 / 800mg / 650mg
30~49歳 / 750mg / 650mg
50~64歳 / 750mg / 650mg
65~74歳 / 750mg / 650mg
75歳以上 / 700mg / 600mg
※出典:厚生労働省 日本人の食事摂取基準2020年版」
表を見ると、年代によってカルシウム推奨量には差があり、推奨量が少ない年代でも、600(mg/日)はカルシウム摂取量を必要としていることがわかります。
しかしながら厚生労働省が実施した調査(※日本人の食事摂取基準2020年版)では、以下のような結果が出ています。
50~69歳男女に、12日間カルシウム摂取量を計測したところ、600(mg/日)以上だった方の割合が、男性46.2%、女性45.0%と調査対象者の半数を切っていました。
また、調査は「600(mg/日)以上」という基準でしたが、実際はこの調査対象の年代の場合、女性は650(mg/日)、男性なら750(mg/日)が必要となるため、結果的にさらに低い達成率になると想定できます。
自己管理ができる大人でさえこの達成率となれば、さらに多くの摂取量が必要となる12~14歳のお子さんの「カルシウム」摂取量は、しっかり保護者の方が気にかけてあげなければ、達成は難しいでしょう。
なぜカルシウムが不足しやすいの?
じつは、「カルシウム」は吸収率が悪い栄養素です。バランスよく栄養を摂っているつもりでも、積極的にカルシウムが多く含まれる食材を選ばなければ、不足してしまいます。
また、日本の水は「軟水」で水に含まれる「カルシウム」含有量が少なく、さらには日本人がよく食べる日本食にはカルシウムが豊富に含有される「乳製品を用いた料理」が少ないこと
も、日本人のカルシウム不足の原因として挙げられます。
推奨量のカルシウムを摂取するには何をどれくらい食べるべき?
では実際にどんな食材をどのぐらい食べれば、1日の推奨量に届くのでしょうか?
一例を挙げてみると、「かたくちいわし田作り」30g(小皿一盛程度)であれば750mg、「焼き油あげ」約10枚で640mg、「ジャージ牛乳」およそ2杯半700mg、「プロセスチーズ」6切れ分(市販のよくある6個入りのチーズ)630mg、「低脂肪無糖ヨーグルト」(小さめの100gカップのもの)5個分650mgが目安です。
ただし同じ種類のものを大量に食べるのは難しく、栄養も偏るため、カルシウム含有量が高い食品を3食にわけて、バランスの良く摂取しましょう。
カルシウムを効率よく補給する方法を知りたい!
食品のなかには、先程紹介した食品以外にも、カルシウム含有量率が高いものもあります。
たとえば、「煮干し」であればたった25g程度で、600mg近いカルシウムが摂取できます。
ですが、煮干しをボリボリと食べるとなると、難しい方もいらっしゃいますよね。
そこで、手軽に効率よくカルシウムが摂れる以下の4つの食品をご紹介します。
牛乳
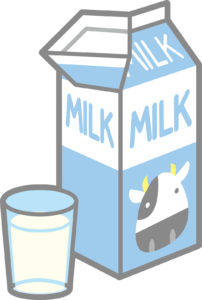
牛乳は「カルシウム」補給には、とても優秀な食品です。先程も紹介したように、たとえばジャージ牛乳であれば、およそ2杯半で700mgの「カルシウム」を摂取できます。
もし、他の食事で「カルシウム」摂取量が足りなければ、気軽に数杯牛乳を飲むだけで1日の推奨量をクリアできます。
たとえば、ホットミルクにしたり、カフェオレにしたりとアレンジのしやすさも魅力です。
オーツミルク

「オーツミルク」はオーツ麦から作られる植物性の飲料で、食物繊維を多く含み、健康志向の方にとても人気が高まっています。
「オーツミルク」は牛乳とカルシウムの含有量に大差がないため、乳アレルギーの方や、牛乳が苦手だという方にもおすすめです。
小魚
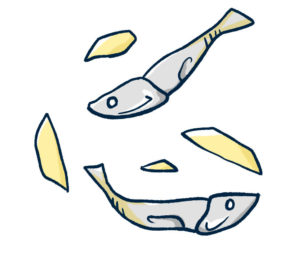
小魚も、「カルシウム」が豊富に含まれる食品の一つです。たとえば「かたくちいわし田作り」30g(小皿一盛程度)であれば、750mg摂取できます。
少量でしっかりカルシウムが摂れるので、副菜に添えてあげると良いでしょう。
小松菜

小松菜はゆでて調理するとおよそ2房で、450mg程度のカルシウムが摂取できます。また生で食べる場合は約510mg含まれています。
小松菜はゆでて使うと、かさも減るため、2房はペロリと食べられるでしょう。手軽にカルシウムを摂取できる食品です。
副菜に使ったり、汁物に入れたりと、こちらもアレンジしやすいところが魅力です。
歯に、お口に、全身の健康に!カルシウムをはじめ栄養バランスのよい食事を!

今回は「カルシウム」を中心にお話していきましたが、紹介した食品は「カルシウム」以外にも「タンパク質」や「ビタミン」なども豊富に含まれているものもあり、どれも栄養満点の食品ばかりです。
歯の健康に良い食事を心がけることはもちろん、全身の健康のためにも栄養バランスの良い食事を積極的に摂っていきましょう。
▼むし歯予防をしたい方は、歯科のメンテナンスへ▼
「むし歯予防のためのプロケアについて」














